日常の関わりから育てるACP
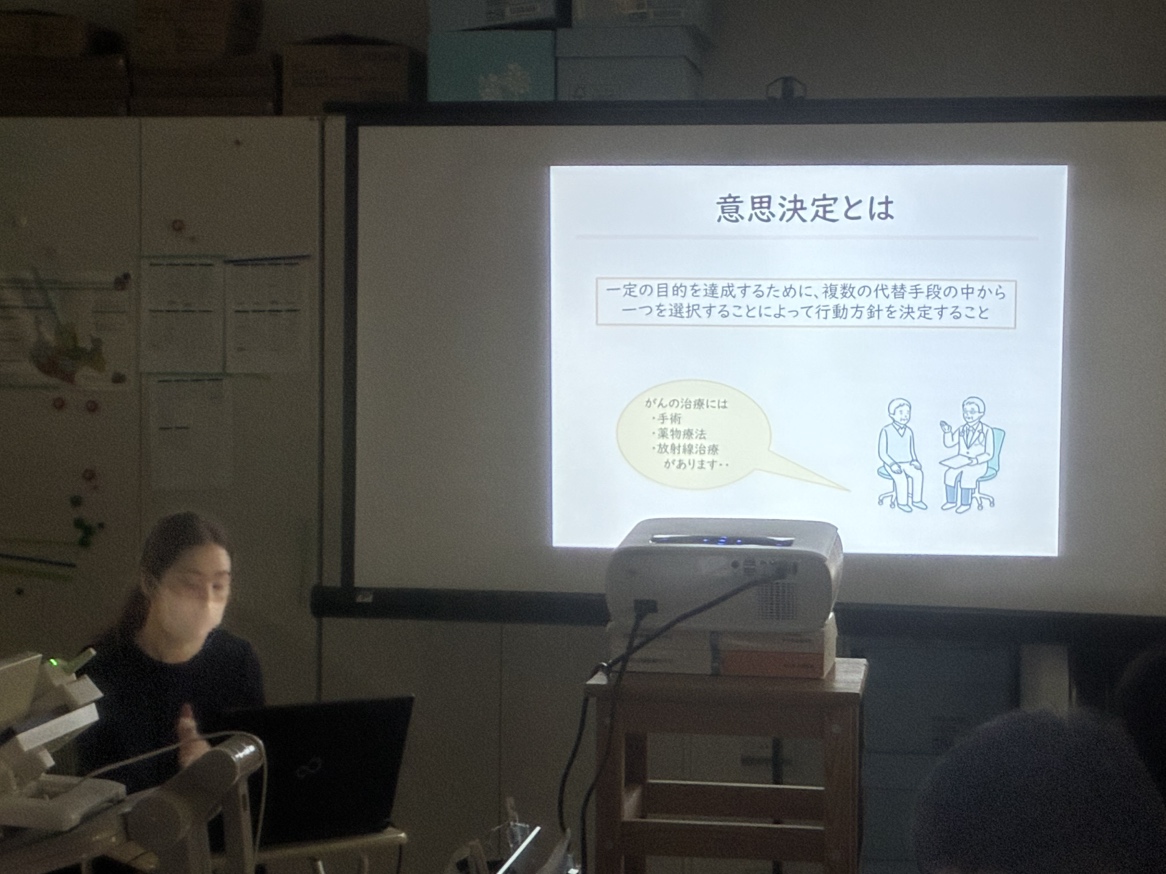
楠の杜訪問看護ステーションは、開設当初から「利用者様に寄り添うこと」「その人らしく生きられるように支援すること」を大切にしています。月1回、業務時間内に意思決定支援についての勉強会を開催し、スタッフ一人一人が利用者さんの意思を丁寧に汲み取り、チームで共有し、全力で支援することができるような取り組みも続けてきました。
しかし、2年前以上に渡る取り組みの中で、アドバンス・ケア・プランニング(以下、ACP)という言葉は敢えて使ってきませんでした。
ACPとは、「将来の変化に備え、将来の医療およびケアについて、本人を主体に、その家族や近しい人、医療・ケアチームで繰り返し話し合いを行い、患者の意思決定を支援するプロセス」。
医療介護従事者にとって大事な概念ですが、元々が英語ということもあり(厚生労働省は「人生会議」と訳して普及活動を行っています)、現場の介護・医療スタッフは「ACPと言われても、実際どこから手をつけたらいいか分からない」「専門的な知識が必要そう」というイメージを抱きがちです。
そんな中、今回は東京都立多摩総合医療センター 緩和ケア認定看護師 白鳥花絵さんをお招きして、「意思決定支援とアドバンス・ケア・プランニング~日常の関わりから育てるACP~」というテーマで、講義と事例紹介をしていただきました。
白鳥さんは昨年度に続き2回目のご登場。昨年度は「グリーフケア」について、心に響くお話をしてくださいました。今回も柔らかな語り口で、それだけでもACPという言葉が温かな響きに聴こえます。

一番心に残ったのは「ACPは特別なものではない」ということ。
限られた介入時間の中で、看護師もリハ職もやるべきことに追われ、「改めて話し合う時間はない」と思いがちですが、白鳥さんからは、「ご本人の価値観、信念、思想、死生観は、実は何気ない会話の中に散りばめられている。日常のケアや対話の中でそれらをキャッチし、みんなで共有して、意思決定支援に活かしていくことが大切」というお話が。
また、治療の中止や心肺蘇生に関すること、療養場所についての意思決定は、丁寧な話し合いの行く末にあるものであって、決してそれらの「決断を迫ること」がACPではないというのにも改めて納得。
「利用者さんや患者さんが病や老いの分岐点に立つ度に、丁寧にご本人の最善を考えて意思決定支援を行うことが、ACPに繋がる」というメッセージ、白鳥さんたちがチームで長期間関わった事例の紹介からも伝わってきました。
ACPの基本は「対話」。これは、利用者さんや患者さん、そのご家族との対話という意味だけではないのですね。在宅と病院を行き来する方を支援するためには、地域と病院のスタッフが顔が見える連携体制を作って対話していくことも重要なんだと思いました。
「日常の関わりから育てるACP」…お話を聴き終えて、この副題が腑に落ちました。ACPという言葉がぐっと身近になった気がします。


